はじめに
会友の金子三典と申します。よろしくお願いいたします。
天文に興味を持ちましたのは、小学生3年生の時です。
もう、60年近く前のことで、教室に先生の天体望遠鏡がありました。
中学生の頃は、天体望遠鏡で月や惑星を見ていました。写真もその頃からでしたが、カメラは父に借りましたが三脚はなく、石ころで傾斜を作って撮影をしました。当然、何が写っているのか分からない写真ばかりでした。
小学校に教諭として就職しましたので、子どもの勉強に使えるかもしれないと本格的に学習に使えそうな天体写真に取り組みました。
ですから、皆様が撮影されている、息をのむような美しい風景と星の写真はなく、星座の形や月や太陽の動きが分かる写真が中心です。
退職を機に、ASPJ 日本星景写真協会へ入会させていただきましたが、自分には全く星景写真のセンスがなく、今でも星座写真を撮影しています。
星座写真
星空写真や星景写真などの言葉は広く認知されてますが、星座写真を楽しんでいる方は少ないようです。
一辺を赤経線か赤緯線と並行になるようにし、北を上にして撮影するなど、いくつかの約束事があります。赤道儀にカメラを取り付けてしまえば簡単に撮影をすることができます。
デジタルカメラに移行した際に、レンズもズームレンズに変更し、格段に効率がよくなりました。ミラーレスカメラ時代になるとF2通しのズームレンズが発売され、飛びついてしまいました。
こと座です。70mm F2.0 ISO6400 8秒露出 フィルターLEE No.5 レンズの前面に取り付け。

縦位置と横位置
星座写真も縦位置と横位置を考えながら撮影をします。その都度カメラを外さないといけません。ところが、赤道儀にがっしりと取り付けてあるのでとても効率が悪いのです。フィルムカメラの時代からカメラ回転装置を使っています。メインで使っている回転装置は大きくて重いですが、90度毎にクリック装置があります。固定で撮影する時は、軽い回転装置を使います。カメラにある水準器は、かなりアバウトな場合が多く、昔ながらの水準器をホットシューに取り付けて使ってます。
手前の3種類が現役の回転装置です。真ん中は大きくて重たいですが、赤道儀に取り付けると安心感があります。また、90度ごとにクリックもついてます。左は赤道儀を持っての遠征用です。クリックはありません。どちらもカメラとレンズに合わせて改造してあります。また、左は最軽量で、カメラ機種専用品です。この軽量品は(後部左)たくさん試しました。

ソフトフィルター
小学生に見せる星座写真には必須のフィルターです。
フィルム時代には、プラ板にクリアースプレーをかけて、自作したりしてみましたが、
結局は、ハリソンソフトフィルターに落ち着きました。ガラス製の重いフィルターで、TIFFEN のフィルターホルダーに入れて使ってました。カメラやレンズを落としたことはありますが、フィルター落下の経験はありません。今でも大切に保管してあります。
デジタルカメラになってからは、LEEのフィルターを裏面で使ってました。ミラーレスカメラと専用のレンズになると好みのソフト具合になりませんでした。レンズ後端と撮像素子が近いことが関係していると思っています。
現在は、LEEのフィルターを前面に入れて使っています。前面にソフトフィルターを入れると四隅の星が伸びてしまいがちです。広角端が28mmなので我慢のできる範囲です。多用するのは、No.4やNo.5です。
前面がハリソンのフィルターです。映画用途だと聞いたことがあります。となりの黒いリングがTIFFEN PROFESSIONAL 82mm-9 ADAPTER RINGです。
他は、お馴染みのLEEのフィルター、ケンコーのPRO1D プロソフトン[A]とよしみカメラのクリップタイプソフトフィルターです。よしみカメラさんは、現在は、ガラスタイプのSTC スターミストフィルターになってます。

背面にソフトフィルターと取り付けて撮影。スピカの星の周りの滲み具合が個人的に気になりました。
写真では分かりにくいですが、滲みと星の間に明確は輪郭が出てしまいます。
よしみカメラさんのクリップタイプのフィルターに変更しましたが、今は、レンズの前面にLEEの取り付けています。

結露とフードとヒーター
星座写真でも結露は大敵です。気づかぬうちに露がびっしりとついていた。そんな経験は何度もあります。撮影場所は舗装されてるところを選びますが、周囲は草原などが多く、一年を通して結露対策は必要です。撮影地の気温や露点温度を表示するアプリも多くあり重宝しています。気温と露点温度の差が5度あるとか風が強いとかの日は、ヒーターも必要ないことがあります。それでもヒーターを使用する方が安心だと思ってます。
レンズフードは内部にヒーター線を入れてます。金属製のフードに穴を開けて内部に線を通してエポキシ系の接着剤で固定してあります。
ただ、F2のズームレンズは95mm径になり、汎用品はありません。現在は、マットボックスレンズフードを取り付けてます。大きなフードですが、内部にヒーター線を入れてあり、休息時にはサンフードを蓋の代わりに使っています。車の横に赤道儀を組み立て、撮影するスタイルなので電源などの苦労はありません。遠征時は昔ながらの桐灰カイロを使っています。
天気アプリには、露点温度が表示されるものがあります。
 以前は、レンズごとに汎用品のフードを買っていましたが、現在はマットボックスを使ってます。取り付けはレンズ径に対応したリングがあります。
以前は、レンズごとに汎用品のフードを買っていましたが、現在はマットボックスを使ってます。取り付けはレンズ径に対応したリングがあります。
桐灰のカイロはフィルム時代から愛用していて、製造中止になる前に大量に購入しました。今でもネット上では販売がされているようです。

ピント合わせ
フィルムカメラの時は、カメラレンズの♾️やナイフエッジでピントを合わせていました。デジタル一眼はライブビューとルーペになりました。ミラーレスの現在は、背面液晶の拡大で合わせています。写野の中の明るい星で大まかにピント合わせをして、微光星で追い込みます。ソフトフィルターを付けてるので、あまり神経質にはなりません。
デジタルに変更した当初はピント合わせに苦労しました。ビデオモードやモノクロモードにするとピントを合わせやすいカメラ機種もりました。
一時期、バーティノフマスクを使ったこともありました。主に天体望遠鏡との組み合わせで使うマスクです。より明るくと思い透明のマスクを自作したりしました。
ピントは遠方の街灯などで合わせていましたが、ズームレンズはマスクを使う頻度が多くてやめてしまいました。
最近知ったのですが、あるメーカーはカメラの電源を入れると無限遠の位置になるとか。レンズは純正で一部のレンズだけかもしれないですが、星屋には嬉しい設定だと思いました。
この原稿を書いてる最中に、「無限フォーカス位置の呼び出し」機能がついたカメラが発表されました。便利な世の中になったと思っています。
ルーペも色々と試しましたが、真ん中のニコン製は今でも時々出番があります。バーティノフマスクは、レンズの口径に合わせてます。最近は透明やフィルターになった製品も多くあるようです。
レンズも天体望遠鏡も開放F値の明るいものが多く、頻繁にピント合わせはしています。

Time Lapse撮影
長時間の撮影になることも多く、ピントの確認やヒーターは必須です。カメラをセットするときにピントリングが動いてしまうことも多く、しっかりとテープで固定しています。
夕暮れ時や明け方に撮影すると明るさの変化が激しくて、思うように撮影できないこともあります。
ホーリーグレイル機能を備えたカメラもあるようで羨ましく思うことも多々あります。
いつも30秒くらいの動画にしたいので、1000枚程度撮影をします。以前、撮影の途中で止まってしまうトラブルを経験したことがあります。多くは電源の問題でしたが、電源をACに変更してもトラブルになったこともあります。少し高級なメモリカードに変更してからは、止まることはなくなりました。Refresh Proという心強いソフトもあるようです。
初期の頃は、スライダーやパンヘッドを取り付けてカメラを動かしながら、Time Lapse撮影をしていました。しかし、子ども達に教材として提示する場合は、景色の動きに注意が引っ張られるようで、やめてしまいました。
太陽と影の動きのTime Lapseです。

太陽の動きや日食撮影
ミラーレスカメラを使って、天体望遠鏡で太陽黒点を撮影して撮像素子が汚れて、3回ほどメンテナンスに出した経験があります。もちろん、減光フィルターは取り付けてはいたのですが。また、円周魚眼や広角で太陽の1日の動きを撮影することもあります。そんな時は一眼レフカメラで撮影をしています。
日食撮影は、赤道儀が小さいので、電子シャッターを使いたいと思います。できれば手も触れたくないです。強者はプログラムを組んでオート撮影をしてますが、そんな知識はないので手動です。せめて、WIFIでカメラをと思っており、昨年は欲張って2台のカメラをiPadとiPhone制御しようと計画をしました。リハーサル時に何度かWIFIが切れてしまいました。BluetoothとWIFIの組み合わせに変更しても思うようにはできませんでした。仕方なく1台はリモートコントローラーで撮影に臨みました。当日、横にいた方は、パソコン制御でした。彼もWIFIは切れた経験があるそうで、パソコンからカメラまでのコードはシールドしてありました。
太陽は、絞りを大きく絞って撮影するかNDフィルターを使って丸く写すかで悩みます。一眼デジカメで撮影をしています。

昨年4月の日食です。薄雲が出て思ったようには撮影できませんでした。8K動画からの切り出しです。

星座早見盤
今日の夜の星空を前もって確認するのに便利です。
パソコンや携帯でも星図ソフトは沢山あり、今夜の星空を確認するには便利な時代になりました。
アナログな星座早見盤ですが、ある日ある時間の星空と同じ位置で、別の日に見る場合に何時になるかを調べるのに便利です。
また、撮影した写真は、別の日だと何時に相当するかを知るのにも頻繁に使ってます。
例えば、12月2日の22時頃だと1月16日の19時頃に同じような星空になります。
16日が晴れるとは限りませんが、今日晴れそうという日だと何時頃になると一目瞭然で分かるので計画、多用しています。
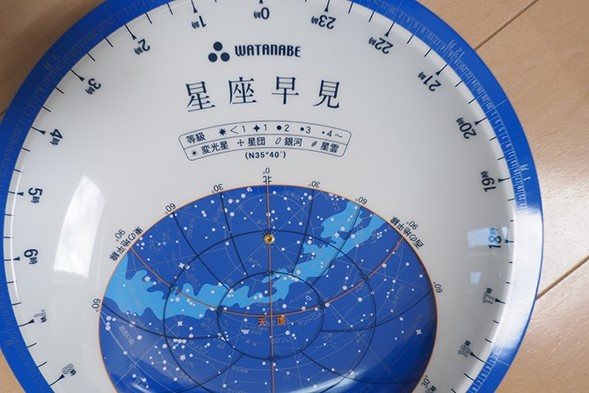
撮影場所
教材に使えるようにと30年近く同じ場所に通っています。最近、立ち入り禁止になり100mほど移動しました。
今年の冬に実施された環境省の「デジタルカメラによる夜空の明るさ調査」の結果が公表されました。九重は国内でもトップクラスの星空です。また、宮崎の清和高原周辺は、国内トップの暗さになります。ただ、天頂付近の空の暗さの測定なので、星景写真のように地上の風景を入れると光の影響を受けます。
先日、宮古島に行きましたが、光害の少ない場所での撮影は気持ちが良いものでした。
北極星の低さに驚き、さそり座が天高くに昇り、感動しました。オオカミ座新星と偶然にも巡り合うことができました。

オーストラリア
若い頃は、レンタカーで移動して撮影をしていました。最近は、バランディーンのツインスターゲストハウスにお世話になっています。仲間とドームを設置し、赤道儀も保管して楽しんでいます。ここは、フェンスで囲まれてますので、安心・安全な場所です。
視力も衰えて南天での極軸合わせが、自分の力ではできなくなりました。電子機器のお世話になってます。一度据えつけたら滞在中はそのままにしてあります。
近隣に星景写真ポイントが数箇所あり、天文雑誌に入選したりしてます。
https://twinstarguesthouse.com
ペンタックスの赤道儀やスカイメモは宿泊者用貸し出し機材です。ペンタックスに取り付けてあるのは、個人のカメラ回転装置です。
赤道儀や電源が自由に使えるので、荷物を減らすことができます。

天空を這うさそり座は、日本では見ることが難しいでしょう。友人が準備中です。

昨年、エアーズロックやデビルズマーブルズに行きました。どちらも撮影禁止区域が広がっていました。神が宿る場所なので仕方ないと思いました。
リモート天文台
オーストラリアには、(株) リコー未来デザインセンター TRIBUS推進室 宇宙映像事業プロジェクトチームのリモート天文台があります。撮影対象を決めて、50cmの反射天体望遠鏡と13cmの屈折式天体望遠鏡と日時などを選び撮影をすることができます。星景写真とは離れてしまいますが、散光星雲や深宇宙を撮影することができ利用しています。
https://www.astrophotography.jp
イータカリーナ星雲 約140分の露出です。

ファイルがfit形式と特殊ですが、おまかせ画像処理も試験運用中です。とても簡単に処理できるので重宝しています。
noteもあります。
https://note.com/astrophotography
おわりに
思いつくままに自分の撮影方法を書いてみました。
山田 卓著 ほしぞらの探訪のりゅう座のページには、「りゅう座の頭は、ヘルクレスに踏みつけられている」とありますが、未だに撮影できていません。
野尻抱影著 日本の星「星の方言集」にも撮影をしたいと思う星のつながりが多くあります。
これからも撮影を続けたいと思っています。
著者:金子三典(かねこみつのり)
福岡県在住 所属(東亜天文学会)
Facebook https://www.facebook.com/mitsunori.kaneko.7
instagram https://www.instagram.com/ef400/?locale=ja_JP











